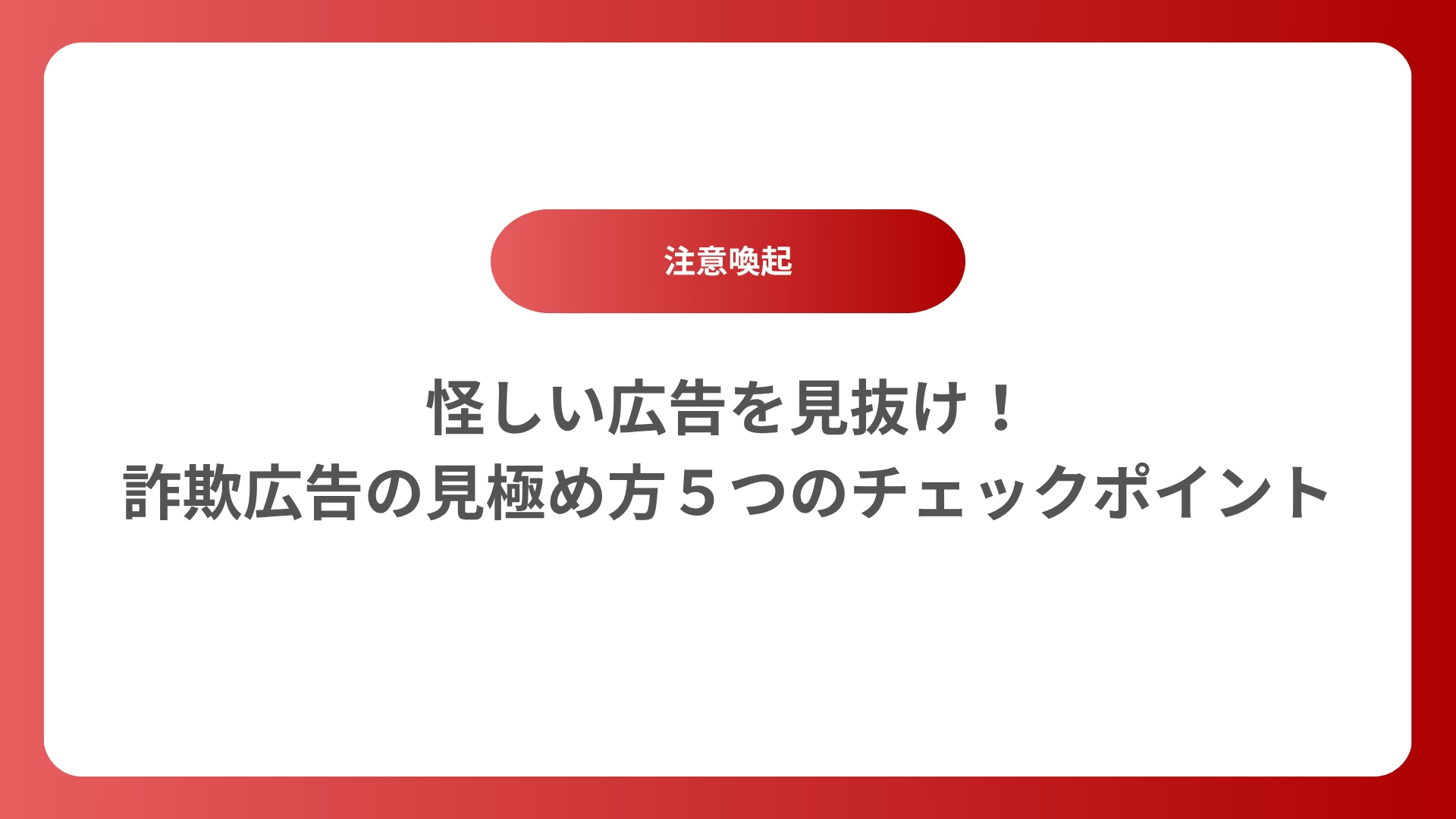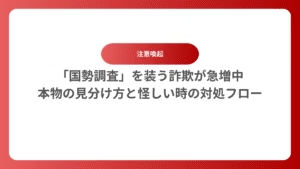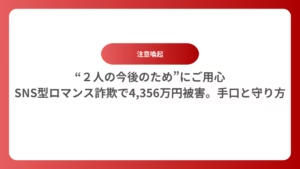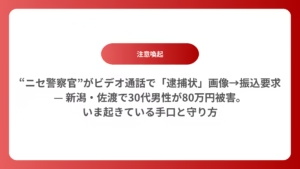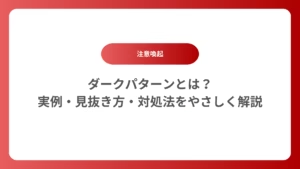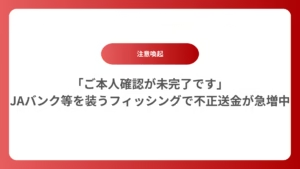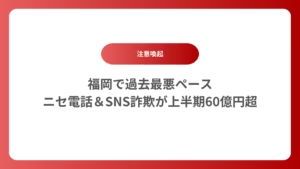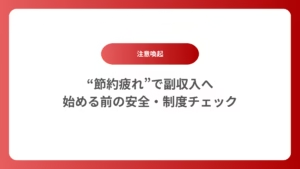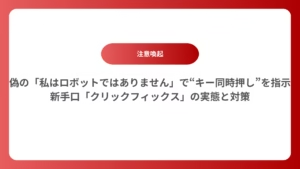こんにちは、よろずやです!
「スマホに出てきた広告をクリックしたら、怪しいサイトに飛ばされた…」
「“今だけ” “誰でも簡単に儲かる”といった甘い言葉に、つい心が揺らぐ…」
最近、ネット上には詐欺まがいの広告があふれています。
しかも、その多くが一見すると「本物っぽい」見た目で、信じてしまいそうになるから厄介。
今回は、そんな詐欺広告を見抜くための“5つの見極めポイント”を紹介します。
目次
🔍 1. 誇張された表現や「限定感」に注意!
以下のような言葉には要注意です。
- 「誰でも月100万円稼げる!」
- 「明日までの限定キャンペーン!」
- 「在庫残りわずか!」
こうした表現は、冷静な判断を奪うための“焦らせテクニック”です。
本当に価値ある商品・サービスであれば、ここまで過剰な演出は必要ありません。
🔍 2. 芸能人や有名企業の“なりすまし”は要警戒
近年増えているのが、芸能人の画像や大手メディアのロゴを勝手に使った詐欺広告です。
- 有名人が実際には推薦していない商品
- 存在しないインタビュー記事風のページ
このような広告は、“本物感”を出して信用させようとする典型的な詐欺手口。
気になったら、公式サイトや本人のSNSを必ず確認しましょう。
🔍 3. URLをチェック!ドメインが怪しくないか?
表示された広告のURLをよく見ると…
- 「.xyz」「.click」「.top」など不自然なドメイン
- 「amazon-co-jp.shop」など、似せた表記(いわゆる“偽アマゾン”)
これらはフィッシングサイトの可能性が高いです。
企業名が入っていても安心せず、URLの綴りや末尾をしっかりチェックしましょう。
🔍 4. 金融商品や副業に関する場合は「金融庁登録」を確認!
投資や副業、資産運用をうたう広告では、その会社が金融庁に登録されているかが大きな判断基準です。
- 金融商品取引業者登録一覧(金融庁HPで検索可能)
- 登録がなければ、違法業者の可能性が非常に高い
広告主の会社名や所在地、代表者名を調べて実在性をチェックする癖をつけましょう。
🔍 5. 「怪しいかも」と思ったら報告・相談を!
少しでも「おかしいな」と思ったら、以下のような対応を。
- 広告掲載元(Google、SNSなど)に「不適切広告」として報告
- 国民生活センターや警察庁「サイバー犯罪対策室」などへの相談
- 金融庁「金融サービス利用者相談室」の利用も有効
一人で悩まず、早めの行動が被害を防ぐカギになります。
✅ まとめ|「うますぎる話」には必ずワナがある
ネット広告は便利な一方で、誰でも簡単に詐欺広告を出せるリスクも抱えています。
- 心を揺さぶるワード
- 有名人の偽装利用
- 違法業者の金融商品
- 不自然なURL
こうしたポイントをチェックするだけで、怪しい広告に引っかかる確率をグッと下げることができます。
「この広告、なんか怪しい…」そう感じたときは、今回の内容をぜひ思い出してくださいね。